日本の水道水のうまさ、キレイさはここまで来ている
水道水の美味しさ キレイさはここまで来ている

ひと昔前までは、汚染水の流れる川から取水しているということで、 水道水はキレイではない、美味しくない、臭いがする、さらには様々な健康を害する成分が含まれている等、水道水は飲めない水といった取り上げ方をする記事や報道が多かったと思います。
しかしながら、その後、各種公害防止対策が総合的に展開されてきました。排水基準を厳格にし定め、排水処理施設の普及・高度化による工場排水の汚れの解消、各種中性洗剤の開発による家庭排水の汚れの解消、薬剤散布や化成肥料の使用による農業廃水の汚染対策、大気汚染防止の進展の結果、大気の汚れが減り、汚れていた大自然、山や森林、草木、あるいはビルや家屋、道路といった建造物の汚れも雨や雪によって徐々にクリーニングされ、結果として雨水や雪解け水も徐々にキレイさを取り戻しつつあります。
その結果、昔の都内のどぶ川は姿を消しつつあります。今ではすっかりキレイになりました。透明度の高い水が流れています。
同様に水道水も、浄水施設の高度化により、定められた浄水基準値を大きくクリアする取り組みが図られ、健康を考えられたキレイな美味しい水が供給されるようになりました。
水道水をペットボトルで販売する浄水場も出てきました
都はペットボトルで水道水を「東京水」として販売しています。金町浄水場の高度浄水100%の水がそれです。
高度浄水とは、通常の浄水処理工程に加えて、オゾンの酸化力と活性炭の吸着力を活用して浄水工程を通常より高度化したものです。その工程でつくりだされている水のことです。
この高度浄水化の流れは、東京都に限らず全国に展開されています。まだ地方によって高度化技術に差があるようですが、間違いなく水質のレベルは確実に上がっているようです。
厚生労働省が制定した「51項目の水質基準」と「基準値」で厳格に管理
水道水には、WHOの飲料水のガイドラインなどを参考にして厚生労働省が制定した「51項目の水質基準」と「基準値」があり、それらの「遵守」と「定期検査」が義務付けられています。
51項目の水質基準のうち31項目は「健康に関する項目」です
細菌や水銀、トリハロメタンなどの人の健康に大きく影響する項目が、
例えば
「大腸菌であれば検出されないこと」、
「水銀であれば0.0005mg/L以下」など、
人が生涯飲み続けても健康に影響しないと考えられる「基準値」が定められています。
51項目の水質基準のうち残り20項目は「生活支障に関する項目」です
味やニオイなど、水道水を美味しく飲めることを目的として基準化されています。濁りなどの見た目についても、定期的にチェックされています。
これに加えて、「よりおいしい」を求めた高度浄水化の流れが、例えば「東京水」を売り出すまでになったわけです。
まだいくつかの問題は残っていますが、これを解決すれば、蛇口をひねれば「キレイな美味しい水」が飲めるという所まで来ているわけです。
このような水道事業に携わる方々の水質へのこだわり、美味しさへのこだわりが「最近の水道水はとてもおいしくなった、きれいになった」という評価につながっているのだと思います。その努力には頭の下がる思いです。

高度浄水を高度浄水として飲むために残された問題点とは
浄水場段階で、水道水に含まれる有害物質が人体に影響しない基準値以下になるよう管理され、水道水がキレイで美味しくなったとしても、問題が無いというわけでもなさそうです。
基準値以下とはいつでも、無になったわけではありませんし、まだ含まれている物質もあるからです。
それに、浄水場から家庭の蛇口間の問題があります。
その1つが、水の消毒の問題です。
安全な水を家庭に届けるために、ウイルスや雑菌の殺菌対策として水道水を塩素消毒します。この塩素は家庭の蛇口まで水とともに運ばれていきます。水中の有機物と塩素が反応すると4種のトリハロメタンを生成します。トリハロメタンは発ガン性を疑われている物質です。これが家庭で飲む水に含まれている可能性があるわけです。
もう一つは、水道管の老朽化の問題です。老朽化すると水質をおとしめる様々な問題が出てくるのです。
水道水の消毒の問題
河川や湖から取水する水道水の原水には、様々なウイルスや大腸菌のような雑菌が含まれている可能性があります。これらの殺菌のために、塩素が使われています。
水道法では、安全性の観点から蛇口時点での水道水中の残留塩素を0.1mg/L以上に保持するよう定められています。また、味やにおいの観点から1mg/L以下という目標値も設定されています。このため、残留塩素の目標を0.3〜0.6mg以下に設定している水道局が多いようです。もちろんこの値は、取水地点の水の雑菌やウイルス等による汚染度により異なります。
水道水に含まれている塩素による健康への影響は、基本的には無いと言われていて、水道水をそのまま飲んでも、残留塩素による健康上の問題は生じないとされています。
しかしながら、害がないとはいえ、例えば時として「カルキ臭」を感じることがあるとおもいますがこれは残留塩素によるものです。カルキ臭は、水そのものでもそうですが、料理等の味やニオイにも影響を与える場合があります。また、ペットの水、金魚の水に使うのを気にされる方も多いと思います。そして何よりも皆さんが一番気にされているのが、トリハロメタンだと思います。
トリハロメタンは、水中の有機物と塩素が反応してできる物質ですが、4種類あります。トリハロメタンは「発がん性物質では」と疑われ危険視されています。
水道管の老朽化の問題
日本中に張り巡らされた水道管網が老朽化しているという問題です。古い水道管が更新されないまま使い続けられている所がかなりあります。
老朽化による問題は2つに分けられます。
①1つ目は、鉛中毒の危険のある鉛成分を溶出する可能性のある鉛配管や赤水の原因といわれている亜鉛めっき鋼管(白管)のような配管が新規素材配管と交換されないで残っていることです。
近年、耐久性が良く、化学的にも安定していて不純物を溶出しないとされている配管材が市場に出されていますが交換工事が進んでいないという現実があります。
②2つ目は、配管そのものが老朽化し、サビたり腐食したりしていることです。昔の水道管の多くは鉄管です。鉄管は水と空気に触れればサビが発生します。これは管内、管外ともにいえることです。
管内に発生しますと水道水にサビ粉が混じる 原因となります。それにこのサビ粉が化学的に安定している塩ビ管等の接続すき間等にとどまりますと貰いサビとして塩ビ管内にサビを発生させます。
管外に発生しますと、腐食の原因になります。水道管も色々なところを通りますので、酸性土壌、アルカリ性土壌、化学成分に汚染された土壌を通ることもあります。こうゆうところで不足が進み、ピンホール等が出来、水道水がまわりに漏れ始めますと酸性水、アルカリ水、汚染水が水道水に紛れ込む可能性もゼロではありません。水道管破裂や土地の陥没等の原因にもなります。
鉛管の交換が終わってないところがあります。
古い水道管のうち、まだ鉛管が残っているところがあります。鉛管は他の水道管に比べると漏れやすく、鉛溶出による鉛中毒の危険もあり、健康面への影響を心配して、現在では新規には使われていません。各地で鉛管の取替え作業が進められていますが、中々進まず、現在でも宅内配管で鉛管が残っている所が多くあるようです。
国の鉛の水質基準0.01mg/1L以下には適合していますが「朝一番の水」あるいは「長期留守」したときなどには、長時間鉛管に水が滞留した状態になりますので、鉛の水質基準を若干超過する可能性があるということで、「最初のバケツ1杯程度は飲み水以外の掃除や洗たくなどの用途にお使いください」といった注意喚起をしている自治体もあるようです。
亜鉛めっき鋼管(白管)の赤水の問題
水道管としてある時期「亜鉛めっき鋼管(白管)」が多く使われていた時代がありましたが、赤水の原因になるということで現在は新規には使われていません。
赤水は水道管内部や継手の腐食により錆が水道水内に溶け出す現象で、亜鉛めっき鋼管を使用した建物に多く発生しています。亜鉛めっき鋼管は内側に亜鉛メッキをして腐食を防ぎますが、水道水内の酸素・塩素の作用によりメッキ層が無くなっていき管を腐食させ、これが赤水の原因となっています。
ライニング鋼管のネジ部、切断部、弁取り合い部の問題
防食処理のなされた塩ビライニング鋼管、あるいは前述の亜鉛めっき鋼管は、管の切断端部やねじ接続部でライニングやメッキ切れが生じて金属部が露出して酸素・塩素の作用をうけ、サビや腐食の原因となります。またこの管に使う弁が黄銅等の異種金属である場合、電位が異なるため腐食やサビの発生原因となる場合があります。
最近使われている配管材 宅内配管材
基幹管路材
現在の水道の基幹管路で最も多く採用されているのがダクタイル鋳鉄管です。近年、耐震性、腐食性、サビにくい、施工しやすいといった観点から適材適所で管材の選択が行われています。
宅内配管材
宅内配管では金属製配管にかわり、サビの発生のないHIVP管やポリエチレン管が多く使われています。
これらは、加工が容易、施工が楽、修理費用も安い、熱や振動・化学物質などにも比較的強いという特長があります。ただ、急激な温度変化に弱く、凍結時には割れやすく、熱で劣化しやすいため給湯管には使用できません。
最近のマンションの配管材
給湯機の普及により温水を使う機会が増えていますが、最近のマンションでは、家庭用給湯コントローラーの上限温度を60℃に設定しているところが多く、キッチン、洗面所、お風呂で使うお湯ではVP管やポリエチレン管等を使用しても問題は無いと思います。
床暖房では温水暖房用架橋ポリエチレン管が使われています。
食洗機の排水管は温度が最高約70 ℃と高いために、耐熱温度の高いHT20管(約90 ℃)等がつかわれています。
水道水タンクの汚れの問題
水道用の貯水槽は水の使用量に応じた水位の上下がありますので密閉構造にはできません。このため、ベント管を設け、そこにホコリが入らないようにフィルターを設けていますが、微生物や菌類の侵入を完全にシャットすることはできないと思います。
昔の団地では屋上に設置されていて、フィルターの性能も今ほど良くはありませんでしたので、ベント部にもホコリがつきやすく、水位の上下で湿気もつき、十分すぎるくらいの太陽の光を受けて微生物が発生しやすかったようです。
マンション各住戸への送水方式
低層の5F建ての送水方式
・低層の5F建てくらいですと、直結給水方式で、水道本管(配水管)から直接各戸へ給水する「直結直圧方式」をとることが多く、貯めることがないので、前述の団地のようなことはおこりません。
15F建ての送水方式
・15F建てくらいですと、直結給水方式で、水道本管(配水管)から直接給水した水をポンプで増圧して各戸へ給水する「直結増圧方式」がとられています。
高層マンションの送水方式
・それ以上の高層マンションになると「受水槽給水方式」がとられています。水道本管(配水管)から、地上や地下に設置された受水槽にいったん貯めて、これをポンプで送水し屋上に設置された「高置水槽」に貯めかえます。この「高置水槽」から各戸へ送水されます。これは「受水槽給水方式」といわれています。
高層マンションの新方式
・高層マンションの新方式として、「直結多段増圧式給水」もあります。15F建てでとった方式を更に進めた方式で、水道本管(配水管)から直接給水し、これを第一増圧ポンプで増圧し各戸へ給水し、上層階で給水圧が足りなくなったら第二増圧ポンプで増圧し各戸へ給水するというもので、理論的には階層の制限はありません。受水槽や高置水槽がないだけ水質管理はやりやすくなると思います。
このように、高層マンションになればなるほど、 各家庭への給水工程は複雑になり、水を汚す可能性は増えていくはずですが、実際にはポンプの改良、弁、継ぎ手、機器の改良等、各種技術の進展により安全性は高まっていると思います。
不純成分の混入、細菌の発生は避けられない
このように、浄水場から高度浄水として送り出された時点と、家庭の蛇口で水を使う段階とを比べると、更新されないで残っている古い配管による有害金属の溶出、蓄積されたホコリ、ゴミ、汚れ、酸化により発生したサビ、細菌の発生、消毒薬である塩素等々が加わり、不純物の含有量は増えることになると思われます。
公害防止対策により、取水口の水質もかなり良くなっています。
浄水場での高度浄水の流れが展開されていますので、浄水場から送り出される水道水の水質ははるかに良くなっています。
配管材、タンク材、弁、ポンプ、フィルター、ポンプ等々、あるいは水道管の施工方法、施工後のメンテナンス等々も、昔に比べればはるかに改善されています。しかしながら、家庭の蛇口で水道事業所の高度浄水をそのまま飲めるかというとそうはいかないと思います。
ここまで読まれた方は、水道水が家庭の蛇口まで届く間に、様々なゴミやサビ、各種溶出成分、雑細菌等が入り込む余地がたくさんあることがおわかりになったと思います。だからといって、その成分量が即健康を害するほどの量ではない事もおわかりになったと思います。
家庭の蛇口に近づけば近づくほど、管内の水は止まっている時と流れている時が明確になり、流れていないときは残塩素等が滞留しやすくなります。
末端の宅内配管では常時水が使われることがないため滞留しがちになります。家庭に送られる水道水には、必ず「塩素」を添加することが法律によって定められています。このため末端の蛇口まで殺菌消毒の塩素が行き届くようになっています。当然の事ながら蛇口付近でのカルキ臭やトリハロメタンの滞留も考えられますのでるわけです。
外出して帰ってきた時、蛇口から水をくみ、うがいしたことありませんか。その時、カルキ臭、あるいは味に違和感を覚えたことはありませんか?
微妙な差で気づかない人も多いとおもいますが、もしも時間を空けた後で水道水を飲用する場合は、少し流して飲用したほうがいいと思います。
まとめ
近年の公害防止策の浸透により、河川や海岸の水がキレイになりました。水道水をつくる浄水場にとって、取水口の水がキレイになるのは良いことです。同じ浄水工程を通る水でも、汚れた水ときれいな水とではその浄水工程に賭ける負担が違います。作り出される水もおのずとキレイさがちがうはずです。加えて、最近の浄水場では高度浄水化の流れの中にあり、よりおいしい水をつくる試みがなされています。
東京都の金町浄水場の高度浄水100%の水は「東京水」としてペットボトル販売されています。今や、美味しい水、キレイな水として水道水を販売できるほどになっているのです。
ここまで来ている水道水ですから、蛇口をひねるだけでで高度浄水を飲める時代もさほど遠くは無いとおもわれます。
水道配管材も新しい材料の管が市場化されていますので、あとは予算を付けて、老朽化した水道管を取り替えていくだけです。
日本全国に張り巡らされた水道管のうち老朽化した水道管、中でも有害物質を溶出する鉛管や赤水の原因となっている亜鉛メッキ管の取り替えを確実にやっていかなければなりませんし、サビや腐食の進んでいる管の取り替え、電位差を発生させやすいい金属の接合の改善等を図り、浄水場からの家庭の蛇口までの間で、新たなサビ、ゴミ、溶出金属、不純物を作り出さないようにしなければなりません。それが家庭の蛇口から美味しい水、キレイな高度浄水が飲めるようになる大前提だと思うからです。
それと、家庭に送られてくる水道水には、必ず「塩素」を添加することが法律によって定められています。基準内の塩素量とはいっても、添加量がゼロではないわけですから、気になる方はこれを浄水器等、別の手段で除去する必要があります。次回では最近建設されているマンションではどういった浄水器が使われいるかを探求してみます。

最近、新たにこんな問題が指摘されています。
1. マイクロプラスチックによる汚染
近年、マイクロプラスチックが水道水や環境中に広がりつつあり、その影響が懸念されています。マイクロプラスチックは、プラスチック製品の劣化や廃棄物から発生し、水源や水道水に混入する可能性があります。これらの微小なプラスチック粒子が人体や生態系に与える影響については、まだ十分に解明されておらず、今後の研究と対策が求められています。
マイクロプラスチックによる汚染 → 「マイクロプラスチック汚染」
マイクロプラスチックが水道水や環境に混入する現象を指しています。
2. 新興汚染物質の検出
医薬品や化粧品、工業用化学物質など、従来の水質検査項目では検出されない新興汚染物質が水道水中から見つかるケースが増えています。これらの物質の長期的な健康影響は明らかでないため、水質基準の見直しや新たな検査方法の導入が必要とされています。
新興汚染物質の検出 → 「新興汚染物質」
医薬品や化粧品、工業用化学物質など、従来の水質検査項目では検出されない新たな汚染物質を指しています。
PFASの環境・健康への影響
PFASは「フォーエバーケミカル(永遠の化学物質)」とも呼ばれ、環境中で非常に分解されにくく、生物の体内にも蓄積しやすいという問題があります。
発がん性の可能性(特定のPFASは発がんリスクを高める可能性が指摘されている)、免疫系への影響(ワクチンの効果低下の可能性)、ホルモンバランスの乱れ(甲状腺機能障害のリスク)、肝臓・腎臓への影響、出生体重の低下、発育への影響等が指摘されています。環境省や厚生労働省が水道水や環境中のPFAS濃度の調査を行い、規制強化を検討中です。
3. 気候変動による水質への影響
気候変動に伴う異常気象や降雨パターンの変化は、水源の水質や水量に影響を及ぼす可能性があります。例えば、豪雨による土砂流入や洪水は、水源の濁りや有機物の増加を引き起こし、水道水の処理負荷を高めることがあります。これに対応するための水道施設の強化や適応策の検討が重要となっています。
気候変動による水質への影響 → 「気候変動による水質汚染」または「気候変動の影響」
豪雨による土砂流入や水質悪化を含む汚染の一種として説明しています。
4. 地域間での水質格差
日本国内では、地域によって水質や水道インフラの整備状況に差があることが指摘されています。特に、過疎地や財政的に厳しい自治体では、水道施設の維持管理が十分に行われず、水質の低下や供給の不安定さが問題となることがあります。これらの地域格差を解消するための支援策や広域的な水道事業の連携が求められています。
地域間での水質格差 → 「水質格差」または「地域間の水質差」
インフラの整備状況による水質の違いを指しています。
これらの問題に対しては、国や自治体、水道事業者、そして市民が協力して取り組むことが、水道水の安全性と持続可能性を確保するために重要です。
これらは現在の浄水器でフィルターで切るのか
現在の浄水器で マイクロプラスチック や 新興汚染物質 をどの程度除去できるかは、浄水器の フィルターの種類 によります。
1. マイクロプラスチックの除去
マイクロプラスチックの大きさは 1μm(マイクロメートル)以下~5mm程度 と幅広いため、以下のようなフィルターで除去できます。
・逆浸透膜(ROフィルター)
→ 0.0001μm程度の超微細なフィルターで、水分子より大きなほぼ全ての不純物を除去できる。マイクロプラスチックは完全に除去可能。
(例)高性能な家庭用RO浄水器、業務用の浄水装置
活性炭フィルター(一部)
→ 物理的なろ過機能を持つ活性炭フィルターのうち、細かいメッシュのものは 1μm以上のマイクロプラスチックをある程度除去 できる。
(例)市販の高性能な浄水器、ブリタなどのポット型浄水器の一部モデル
⚠ 除去が難しいフィルター
× 一般的な活性炭フィルター → 大きめのマイクロプラスチック(1μm以上)は除去できても、ナノサイズのものは通過する可能性がある。
× 簡易型フィルター(水道蛇口型やポット型の簡易なもの) → 目の粗さによってはほぼ除去できない。
2. 新興汚染物質(医薬品・化学物質など)の除去
・逆浸透膜(ROフィルター)
→ 医薬品成分や化学物質の多くを除去可能。最も効果的な方法。
(例)高性能なRO式浄水器
・活性炭フィルター(高性能なもの)
→ 一部の医薬品成分、農薬、揮発性有機化合物(VOC)を吸着し、ある程度除去可能。
(例)高品質な家庭用浄水器、業務用フィルターシステム
⚠ 除去が難しいフィルター
× 一般的な活性炭フィルター → 一部の化学物質しか除去できない。
× 陶器フィルター、単純なセディメントフィルター → 微細な化学物質は通過してしまう。
3.PFASの除去
PFASを除去できる水道水フィルターとは?
PFAS(ペルフルオロアルキル化合物)は非常に分解されにくく、水道水にも混入するリスクがあります。そのため、家庭での飲料水対策としてPFASを除去できるフィルターの使用が推奨されています。
マイクロプラスチックや新興汚染物質の除去に対応した浄水器
ライフプラス 浄水器 カウンターオン・タイプ(モデル MP400 SSCT)
高度なカーボンブロックフィルター技術を採用し、微生物、残留農薬、重金属、塩素、マイクロプラスチック、ホルモン剤などを除去します。
ブリタ
マイクロディスク 浄水フィルター
ヤシ殻由来の天然活性炭フィルターを使用し、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質、15μm以上のマイクロプラスチックなどの微粒子をろ過します。
キッツマイクロフィルター GOQURIA(ゴクリア)
独自のフィルター技術を活かした4層ろ過構造で、PFASの一種であるPFOS/PFOAを除去しながら、ミネラル分は透過します。
トレビーノ アクアマイスター(型番 AMC.50XJ)
専用カートリッジにより、0.1マイクロメーター単位の微細な濁り成分、トリハロメタン、溶解性鉛など13物質の除去に対応しています。
アールイオス(ř-eos) 逆浸透膜浄水器
不純物を取り除いた「純水」を作ることができる逆浸透膜浄水器で、安心・安全な水を提供します。
PFASを除去できるフィルターの種類
活性炭フィルター(Granular Activated Carbon, GAC)
仕組み:多孔質の炭がPFASを吸着
効果:PFASの長鎖化合物(PFOA、PFOS)に特に有効
例:浄水ポット型フィルター、蛇口取付型フィルター
注意点:定期的なフィルター交換が必要
ブリタ マイクロディスク 浄水フィルター
逆浸透膜(RO: Reverse Osmosis)
仕組み:極小のフィルター膜で水分子以外を除去
効果:PFASを約90%以上除去可能
例:アンダーシンク型(シンク下に設置)、業務用浄水装置
注意点:廃水が出るため、効率がやや低い
イオン交換樹脂
仕組み:化学的な吸着作用でPFASを除去
効果:特定のPFASに有効(家庭用にはあまり普及していない)
例:工業用浄水装置、自治体の水処理施設で使用
家庭用でおすすめのPFAS対応フィルター
① 活性炭フィルター(手軽に導入可能)
ブリタ(Brita) や トレビーノ(Toray) などの浄水ポット
蛇口取付型フィルター(例:クリンスイ、ピュリタン)
冷蔵庫内蔵の浄水フィルター(対応モデルのみ)
② 逆浸透膜(RO)フィルター(本格的な浄水)
ピュリテック(Puritech)
アクアサナ(Aquasana)
国内メーカーのRO浄水器(例:三菱ケミカル・クリンスイのROタイプ)
PFAS対策のポイント
フィルターの交換を忘れずに(古くなると吸着能力が低下)
水道水のPFASレベルを確認(自治体の水質検査情報をチェック)
可能ならROフィルターの導入を検討(特にPFAS汚染が深刻な地域)
これらの製品は、マイクロプラスチックや新興汚染物質の除去に効果的とされています。ただし、各製品の性能や仕様は異なるため、詳細は各メーカーの公式サイトや製品情報をご確認ください。
情報源


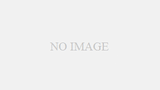
コメント